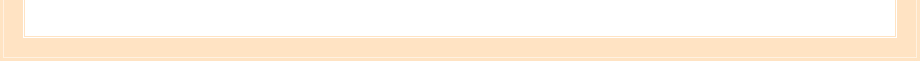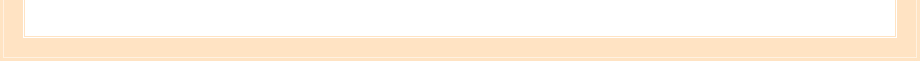世界中に衝撃が走ったボブ・ディランのノーベル文学賞受賞。
彼は1962年のデビュー以降多くの人々に影響を与え続けていますが、
かつてヤドランカも彼に傾倒していた若者の一人でした。
1960年代、世はベトナム戦争の真っただ中。
高校卒業間近に休学し、叔父のバンドに参加していたヤドランカは
西ドイツのラムシュタインにあったヨーロッパ最大のアメリカ空軍基地で
演奏し歌っていました。(その後フランクフルト、ベルリンのキャンプ等でも演奏)
ヤドランカは基地のアイドルとして圧倒的な人気を得ていましたが
彼女自身は、基地で歌うことに複雑な思いを持っていたそうです。

「自分は子供だったからどうすることもできなかった…」
とヤドランカは言っていますが、
彼女は夜は基地で兵士の為に歌い、昼はハーモニカとギターを持って反戦デモに行くという相反する演奏生活をしていました。
誰かの為に、自分の信念の為に精一杯できることをする。そこに彼女らしさを感じます。
米兵の中にもヤドランカと同じように、キャンプでは兵士であるけれど、街では軍服を脱ぎ捨てて反戦デモに加わっている人もいて、ヤドランカは彼らとも友達になったそうです。
ベースキャンプや反戦デモで、彼女が歌っていたのがボブ・ディランの「風に吹かれて」でした。
ヤドランカは時を経て、日本でのコンサートでも度々この曲を歌っています。
このエピソードは「アドリア海のおはよう波」(ヤドランカ・長原啓子共著)で語られています。
この本はヤドランカのことだけでなく、彼女の友人である長原啓子さんによって
複雑な旧ユーゴの歴史や文化もわかり易く書かれている良書です。
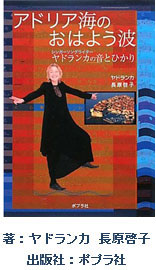
長原さんによると
ステージでも時々ハーモニカを吹いたのは、ボブ・ディランへのリスペクトだと、
ヤドランカは話していたそうです。
ところで、ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞をうけて、ここのところ多くのメディアで彼の音楽の文学性について取り上げられています。
12月10日の朝日新聞に音楽評論家の萩原健太さんと、フォーク歌手の中川五郎さんの対談記事があったのですが、中川さんは以下のように語っていらっしゃいます。
「誤解を恐れずにいえば、ディランの歌にはすべて“元”がある。古いトラッドやフォークソング、黒人霊歌、ゴスペル、ブルースといった民衆の音楽。そうしたものを下敷きに自分なりに手を加えていく曲作りを彼は続けている。決して独創性がないわけでなく、彼が魔法の粉をふりかけると、眠っていた古い曲が時代と共振・共鳴する新たな歌になる」
これはヤドランカにも言えることです。
ヤドランカの追悼盤「Hvalaフヴァーラ」には各地の古い民謡をリメイクしたり、ヤドランカ独自の解釈で歌ったものを中盤に連続して収録しました。
旧ユーゴの民謡を再構成した「アンジョ」「砂漠のエトランゼ」「エレノ」、ブラジル北東部に伝わる「マナ」、そして日本の八王子市周辺に江戸時代から伝わる「鮎かつぎ唄」。
“元”の歌を独創的に新たな作品に蘇らせる才能はヤドランカのひとつの大きな特徴です。
それぞれを聴き比べながら歌の旅をしてみるのも、このアルバムの楽しみ方でしょう。

朝日の対談では萩原健太さんがこんなことも話されていました。
「ディランはランボーやギンズバーグなどのビート詩人やフェリーニの映画からの影響、絵画のような色彩感も彼の言葉にはあると言われている」
まさにヤドランカも、昔の詩人にインスパイアされ素晴らしい作品を生み出しています。
そして画家でもあるヤドランカの音には色彩があふれているのです。
ボブ・ディランに憧れたあの日の少女は、素晴らしい作品の軌跡を遺してゆきました。
|